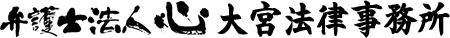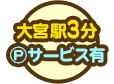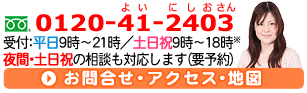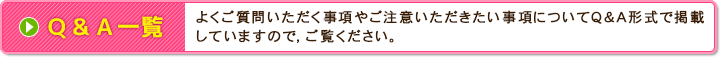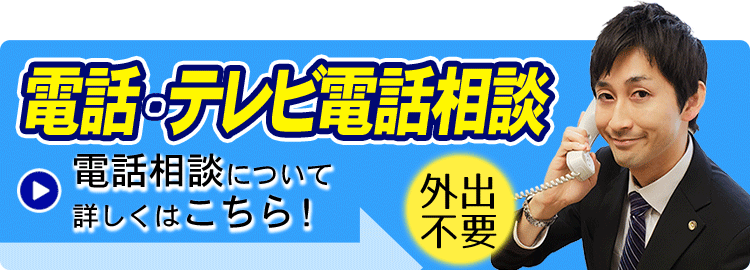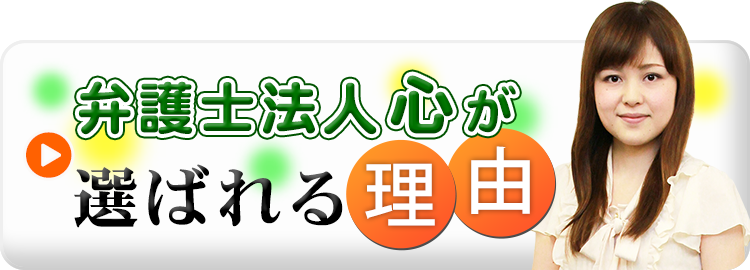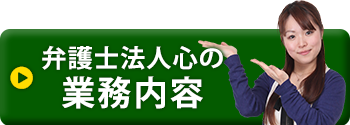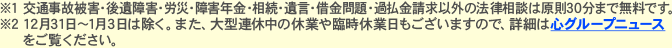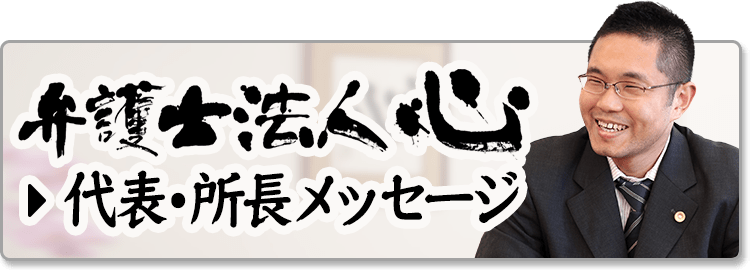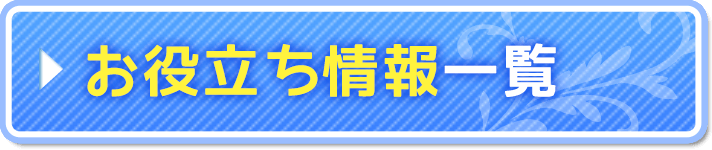交通事故に遭った主婦が請求できる損害賠償
1 主婦休損が請求できる場合があります
交通事故に遭い、けがを負った方が主婦あるいは兼業主婦であった場合には、交通事故によるけがで家事ができなくなった分について、家事従事者としての休業損害、いわゆる主婦休損を請求することができる場合があります。
確かに現実的には家事を行うことによってお金がもらえるわけではありませんが、扶養義務のある家族のために家事を行っているということを捉え、交通事故によって家事ができなくなった分については、主婦休損として請求することができるというのが裁判例上の考え方となっております。
このように家事は基本的に家族のために行う必要がありますので、一人暮らしで自分のためだけに家事を行っていたとしても主婦休損を請求することはできません。
2 兼業主婦でも主婦休損が請求できる場合があります
家族のための家事を行いながら、パートやアルバイトをされている、いわゆる兼業主婦の方も多いと思います。
このような兼業主婦の方であっても主婦休損を請求できる場合があります。
一般的に、兼業による1週間の労働時間が30時間以上ある方の場合には、フルタイム勤務の給与所得者として休業損害が請求できるにとどまり、30時間を超えない方の場合には、主婦休損として休業損害が請求できます。
なお、兼業の休業損害と主婦休損のどちらも請求できる場合には、いずれか高い方が請求できるというのが一般的です。
3 主婦休損の計算方法
自賠責基準における主婦休損の計算方法は、日額6100×実通院日数(実際に通院した日数)=休業損害額で算出されることになります。
裁判所基準の場合には、これといって決まった算定方法はあるわけではありませんが、裁判例上いくつかの計算パターンがあります。
例えば、事故当年の平均賃金日額×実通院日数×〇%(家事への支障の程度)=休業損害額で算出する方法があります。
他にも、総治療期間を家事への支障の程度の割合で傾斜をつけて計算するという算出方法もあります。
事故当年の平均賃金日額×10日×80%+事故当年の平均賃金日額×20日×60%+事故当年の平均賃金日額×30日×40%=休業損害額といった具合です。
主婦休損をどのような計算によって算出するかについては、このように通院状況や家事への支障の程度等に応じて判断する必要があります。
そのため、そもそも主婦休損を請求できるのか、請求できるとすればいくらなのか、といった点でお困りの際には、弁護士に相談することをおすすめいたします。
高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ 交通事故における慰謝料の相場について